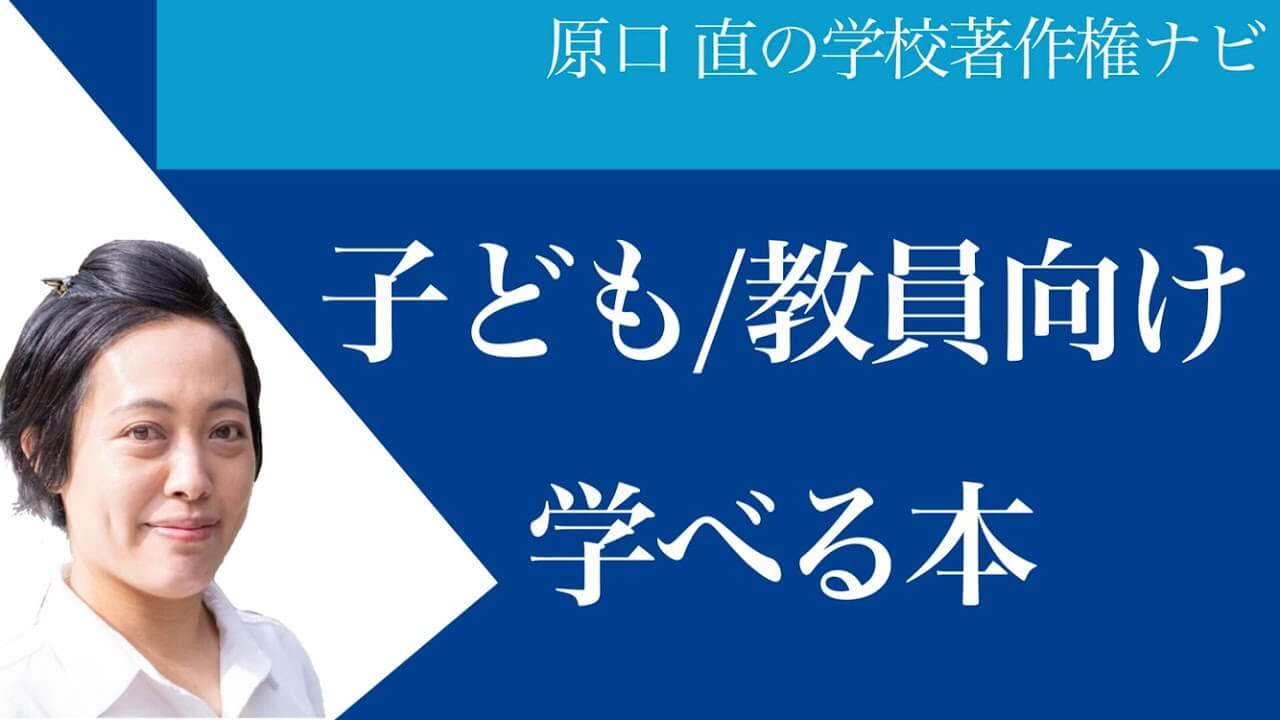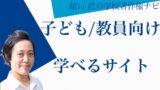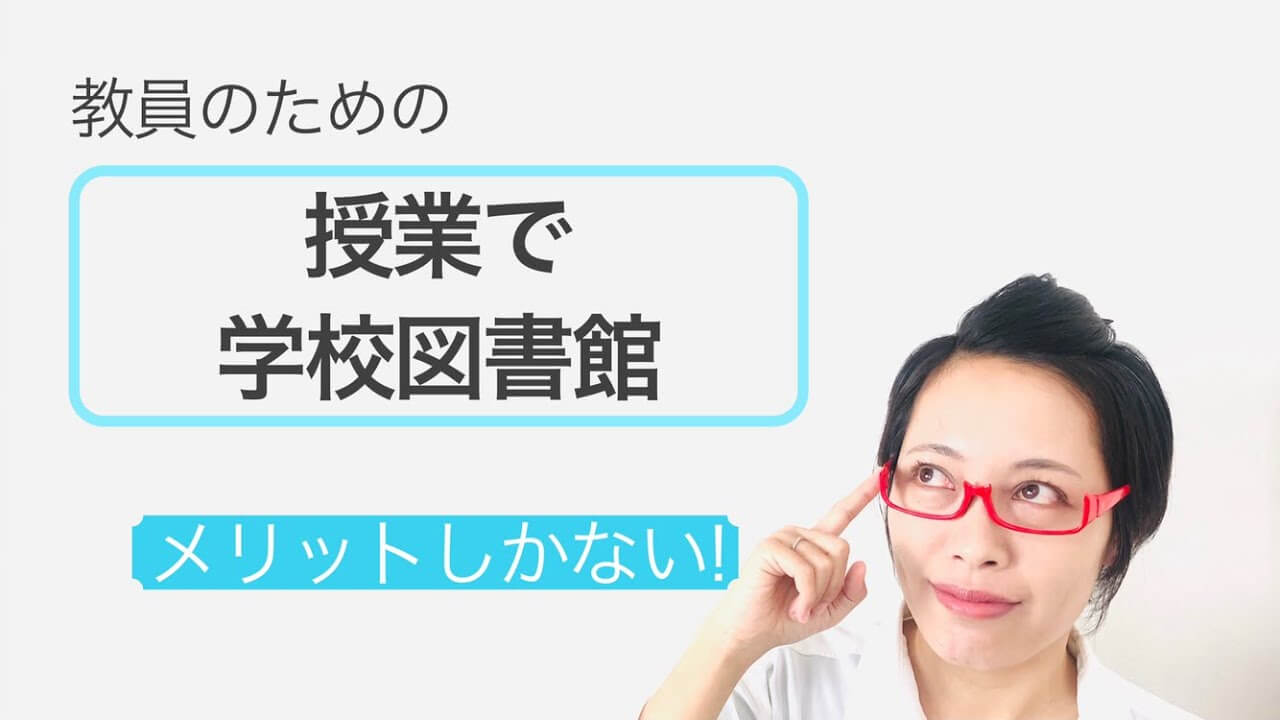著作権の学びにおすすめの本を3冊ご紹介します!
私は弁護士や弁理士ではなく、法学部出身でもありません。持っているのは学校現場での経験です。つまり、子どもや保護者、教員に対して、いつ・どの程度・どのように説明すればよいかがわかるということ。また、学習指導要領における知的財産権・著作権の位置づけや、教科書や教員採用試験への関わり、そして授業実践の経験があります。
大学卒業後に著作権を学び始め、書籍やサイト、動画などを頼りに学習してきました。今回は、法律の素人として著作権を勉強する際に役立った書籍を3冊ご紹介します。
著作権を勉強する際に役立つウェブサイトについては、別の動画「【子ども・教員にオススメ】著作権を学ぶおすすめウェブサイト4つを紹介」で紹介しています。あわせてご覧ください。
著作権を学べる本を選んだ視点
著作権に関する書籍は、法律書から判例解説まで様々あります。その中から、学校に関わる著作権に焦点を当て、「子どもも教員も保護者も学べる」視点で3冊を選びました。
最初の2冊は、中学3年生の音楽科の授業で調べ学習用に使用した本で、地域や大学の図書館から取り寄せた50冊以上の中から、学校司書さんが特におすすめとして選んだものです。中学生の発達段階や好みに合わせて選書された、信頼できる一冊です。
なお、著作権法は2018年に2回、2020年に1回、2021年に1回と度重なる改正がありました。今後も変更の可能性があるため、情報の発表年・出版年には十分ご注意ください。
読むべき本①『18歳の著作権入門』(福井健策 著/2015年/筑摩書房)
私が著作権の学びを始めた最初の本であり、学校司書さんが教材研究の段階で勧めてくれた一冊です。中学生の授業でも活用し、生徒たちがうさぎのキャラクターを題材に議論するなど、興味を持って読み進めていました。
第1部の基礎知識編では、「著作物って何?」という基本から、「著作権ってどんな権利?」「著作権侵害だと何が起きる?」まで、わかりやすく解説されています。特に、「どこまで似れば盗作なのか」という問いは、キャラクターの事例を通じて考えさせられます。
第2部の応用編では、「ソーシャルメディアと著作物」「動画サイトの楽しみ方」「JASRACと音楽利用」など、生徒に身近な話題が豊富。著作権の基本から応用まで、一冊で幅広く学べます。
読むべき本②『すべてのJ-POPはパクリである』(マキタスポーツ 著/2014年/扶桑社)
音楽好きの中高生におすすめの一冊。吹奏楽部や軽音楽部、YouTubeやサブスクで音楽を楽しむ生徒に大人気でした。著者のマキタスポーツさんは芸人でありながら音楽活動にも取り組み、「J-POPはすべてパクリである」という刺激的な視点から、音楽と著作権を読み解きます。
第1章ではヒット曲の法則、第2章ではCDが売れなくなった背景やアイドルの楽曲分析などが語られます。第3章はモノマネからのオリジナリティ、第4章ではポップスとノベルティソングの関係など、著作権をエンタメ視点で学べる内容です。
難しい言葉を使わず、「パクリ」という言葉を切り口に著作権に触れられるこの本は、子どもから大人まで楽しく学べる良書です。
読むべき本③『著作権ハンドブック、先生勝手にコピーしちゃダメ』(宮武久義・大塚大 著/2021年/東京書籍)
改正著作権法に対応し、2021年12月時点で最新の学校向け著作権解説本です。
序章では「オンライン授業と変更された教育現場の著作権ルール」を取り上げ、第1部では「5分でわかる著作権の基礎知識」として、「夏休みの作文にも著作権がある?」「すべてのコンテンツが保護対象?」などを簡潔に解説。
第2部は「著作権の常識・非常識」として、教育機関での適用や第35条の運用指針について、一問一答形式でまとめられています。読みたいところから読むことができ、興味の輪が自然に広がる構成です。
子どもでも読めるやさしい記述もあり、家庭や教室で活用しやすい内容となっています。
「【教員のための著作権解説】SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」
「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」
まとめ:著作権を学ぶ第一歩に本を活用しよう
著作権は法律であり、難しい表現も多い分野です。だからこそ「翻訳」が必要だと感じています。法律家と教員の間で言葉や状況の理解がずれると、せっかくの学びの機会が失われてしまいます。
「相談したけど分からなかった」は「もう相談しない」に繋がります。そうならないよう、両者の橋渡しをする「翻訳家」の役割が大切です。
これからも、学校と著作権をつなぐ翻訳家として、情報発信を続けていきます。著作権をめぐる知識は、教職員・保護者にも必要なもの。ぜひ、研修や講演もご活用ください。
このサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【教員・生徒・保護者必見】著作権を楽しく学べる本3選!授業実践でも大活躍!」も是非ご覧ください。