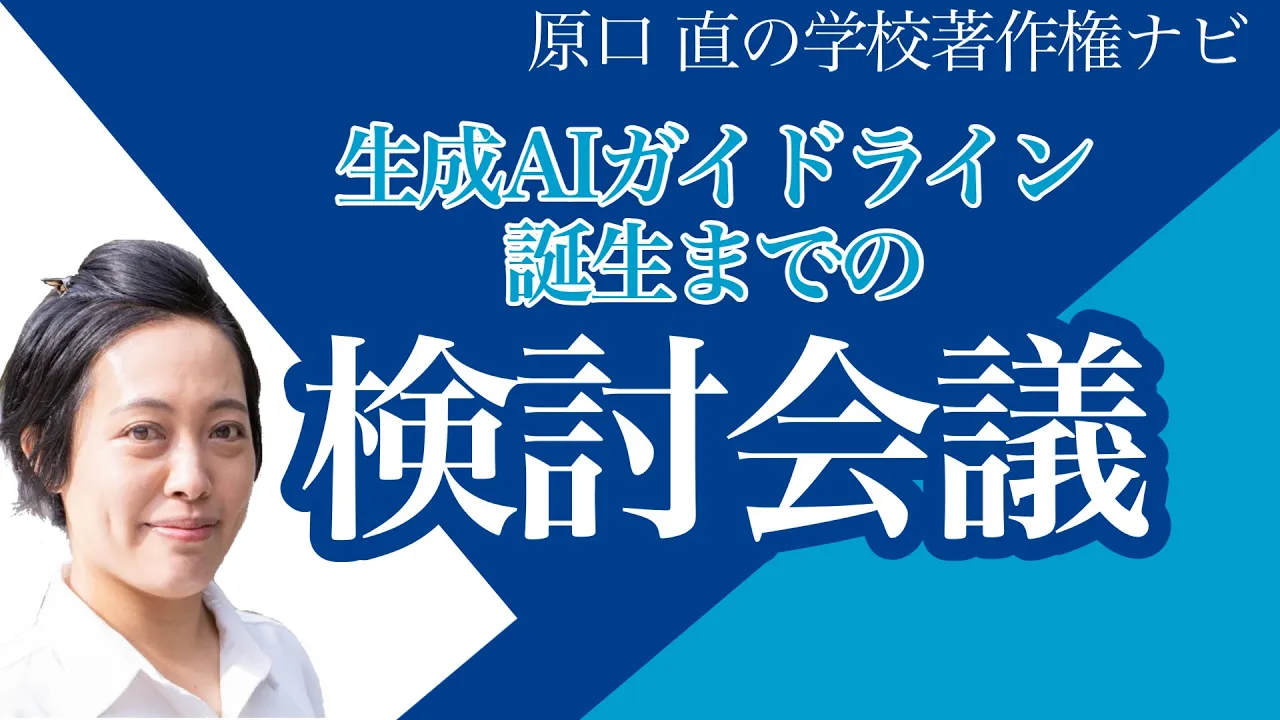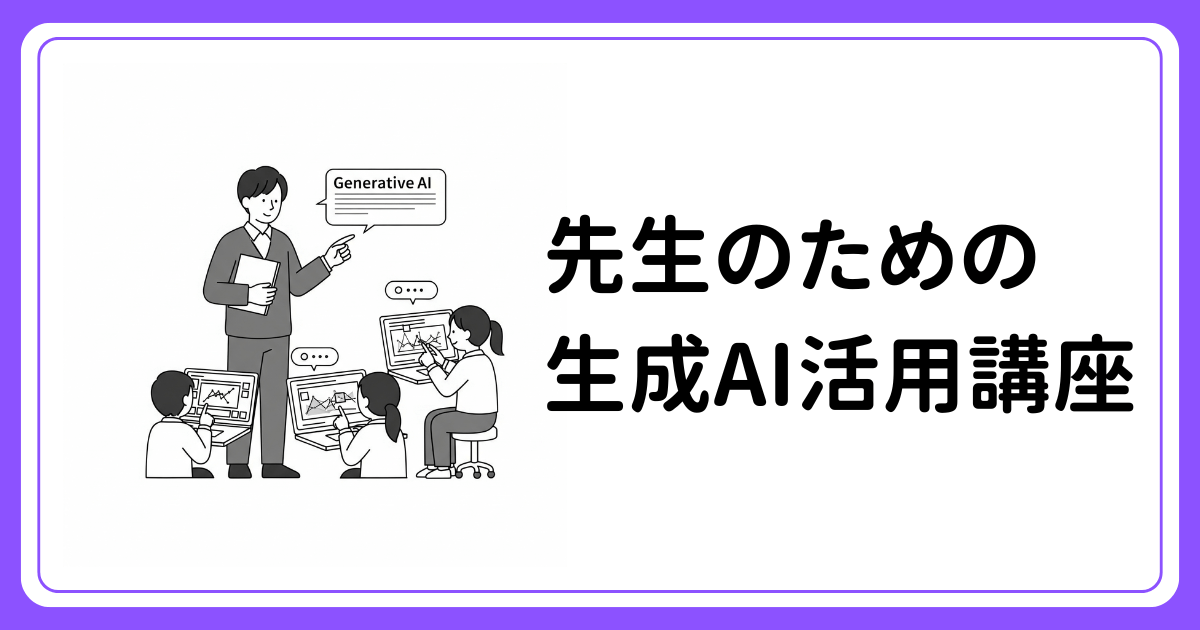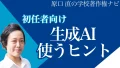「AIを学校でどう使う?」「使わせる?」
今、教育現場で注目を集める「生成AIの利活用に関するガイドライン」。令和6年12月に文部科学省から公表されたこの指針は、私たちの働き方や子どもたちの学びを大きく変える可能性を秘めています。

でも、このガイドラインはいったいどのようにして生まれたのでしょうか?
今回は、その道のりを辿るべく、文部科学省が設置した「初等中等教育における生成AI利活用検討会議」での議論の内容を分かりやすくご紹介します。全7回にわたる会議で、教育やAIの専門家、そして現場の先生方がどのような意見を交わしてきたのか、その一部を覗いてみましょう。

議論の変遷:半年間で何が変わった?
この検討会議は、約半年間の間に全7回開催されました。
その中で、生成AIの利用方法、教員の役割、教育現場の格差、ガイドラインの対象者、形式、有効期限、そして安心安全に関わる重要な論点が浮き彫りになり、議論が深まっていきました。
AIの利用方法:知識伝達から創造性育成へ
当初、AIの利用は知識の伝達に重点が置かれていましたが、議論が進むにつれて、創造性や問題解決能力、批判的思考を育成することの重要性が強く認識されるようになりました。
AIを単なる情報源として捉えるのではなく、子どもたちの可能性を引き出すためのツールとして活用することへの期待が高まっていると言えるでしょう。
教員の役割:AIリテラシーから学びのサポートへ
教員に求められる役割も変化しました。
当初はAIリテラシーを身につけることが重視されていましたが、会議が進むにつれて、AIを効果的に活用し、子どもたちの学びをより深くサポートする役割が重要視されるようになりました。また、教育委員会が教師を支援する体制づくりも不可欠であるという意見も出ています。
教育現場の格差:情報共有と研修機会の均等化へ
教育現場における格差是正の重要性も、議論を通じて強く認識されました。
地域や学校間の格差を小さくするために、情報共有や研修の機会を均等に提供する必要性が指摘されています。誰もがAIの恩恵を受けられるような環境整備が求められています。
ガイドラインの対象者と形式:より広く、より分かりやすく
ガイドラインの対象は、当初の学校関係者だけでなく、保護者や一般社会への影響も考慮すべきという意見が出ました。家庭での生成AI利用や保護者の理解の重要性が指摘されています。
また、ガイドラインの形式についても、詳細な記述から簡潔で分かりやすいものへと変化が求められ、事例集や解説を別途作成する提案もなされました。
ガイドラインの有効期限と安心安全:変化への対応とリスクへの備え
生成AI技術の急速な進歩を踏まえ、ガイドラインの有効期限に関する議論も行われました。
当初の暫定的な改定という考え方から、必要に応じて一部改定を加えていくという柔軟な対応へと変わってきています。
また、「完全な安全はない」という前提のもと、試行錯誤しながらリスクを理解した上で生成AIを積極的に活用していくという考え方が共有されました。
個人情報の取り扱いや著作権侵害のリスクへの対応策も重要な議題となりました。さらに、倫理的な観点から、環境負荷や生成AIへの依存といった問題も議論されています。
ポジティブな意見とネガティブな意見:多角的な視点
検討会議では、生成AIの活用に対して、ポジティブな意見とネガティブな意見の両方が出されました。
ポジティブな意見
- 教育に大きなインパクトを与え、児童生徒や教員のより良い人生のために貢献できる。
- 外国籍の児童生徒や保護者とのコミュニケーション、特別支援教育において有効活用できる。
- 教員が使い始めると児童生徒も学び始め、主体的な学びや興味関心を育むきっかけになる。
- 授業で活用できるツールであり、本物の問いを見つけ解決する力を養うのに役立つ。
ネガティブな意見
- 経験の浅い子供や学生はリスクを抱える可能性がある。
- ガイドラインが授業改革につながらない場合、宝の持ち腐れになる可能性がある。
- 生成AIがインフラになった際、学校でどこまで教育する必要があるのかという疑問。
- 保護者が利用に同意しない場合の対応を示す必要がある。
- 安易な解答への依存は、子供の多様性や創造性を損なう可能性がある。
- ハルシネーション(もっともらしい嘘)や著作権侵害のリスクがある。
- 情報活用能力が十分に育成されていない段階での利用には懸念がある。
- 環境負荷やコストの問題を考慮する必要がある。
- 最終版としてのガイドライン作成に違和感があり、変化への対応が必要である。
まとめ:検討会議から見えてくること
検討会議の議論を通して、生成AIは教育現場に大きな可能性をもたらす一方で、慎重な対応が必要であることが改めて確認されました。
初期段階では、情報活用能力が十分に育成されていない段階での利用に対する懸念が強く表明されていましたが、議論が進むにつれて、情報活用能力を育成しながら生成AIを適切に活用していくことの重要性が強調されるようになっています。
文部科学省のウェブサイトでは、この検討会議の議事録が公開されています。ぜひ皆さんも目を通し、生成AIの活用について、そしてこれからの教育について、ご自身の考えを深めてみてください。
この記事の内容を、Youtube動画「【最新情報】学校のAI活用、どう進める?文科省ガイドライン検討会議の重要ポイントを先生向けに解説」で詳しく解説しています。