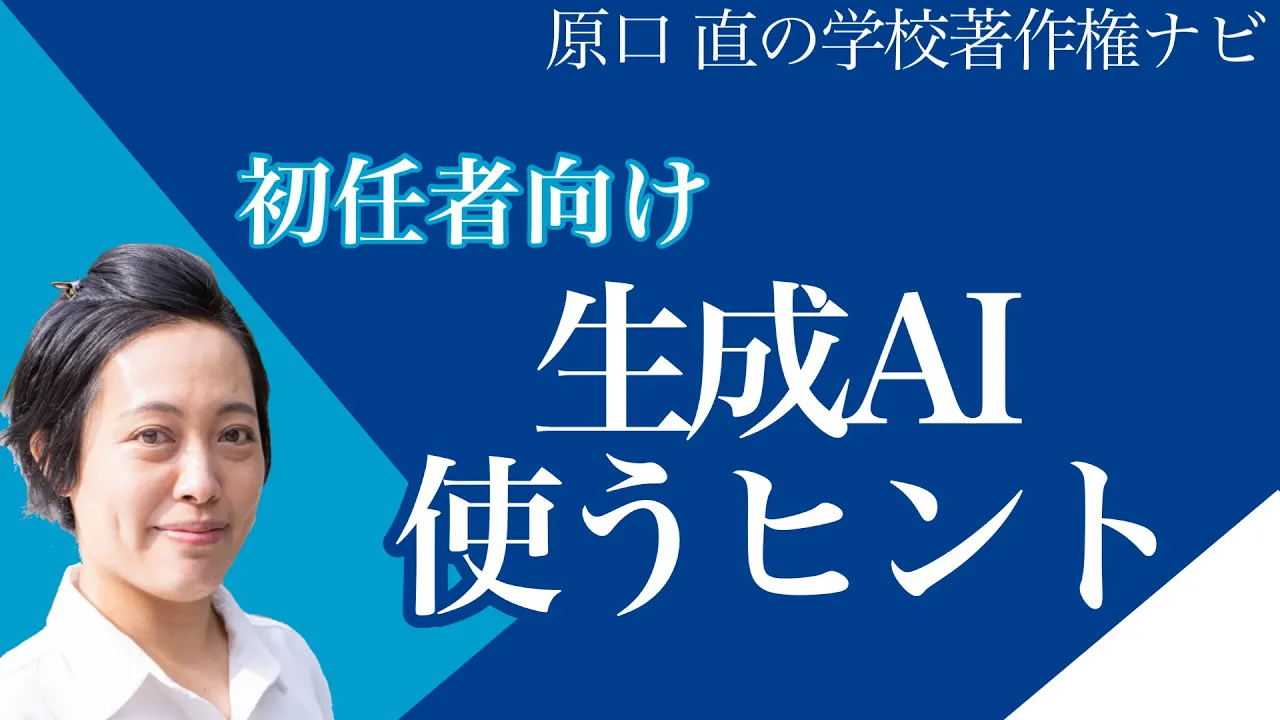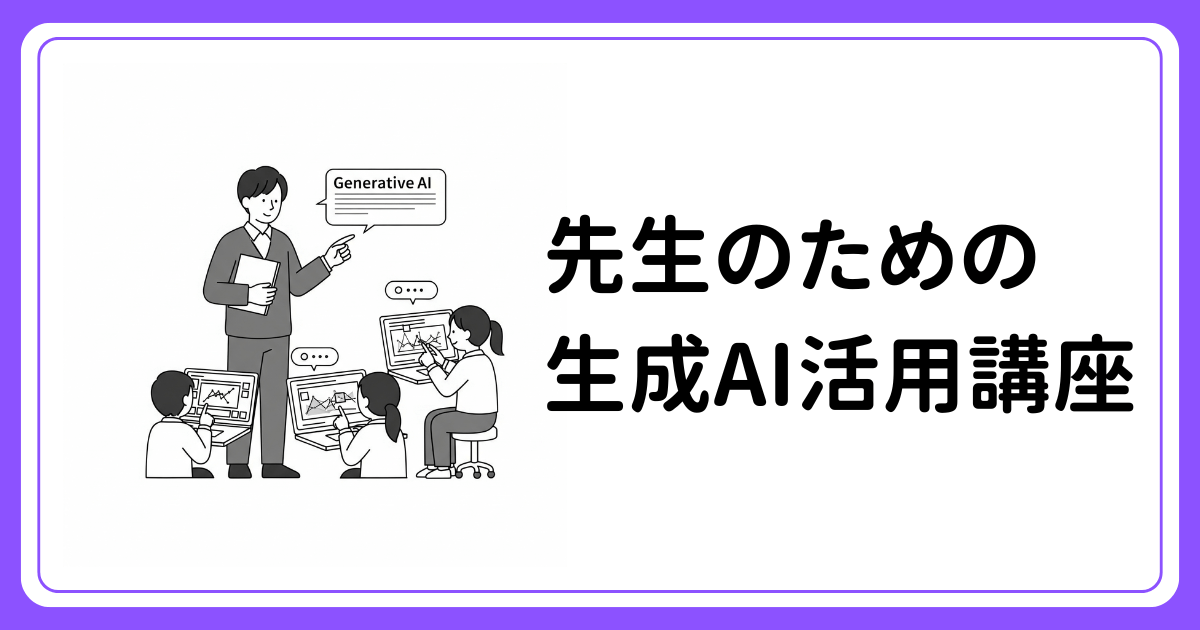近年、生成AIが社会全体で注目を集めています。その波は学校現場にも及び、教職員としても活用方法や注意点を理解しておく必要があります。
この記事では、生成AIの基本的な説明に加え、授業や校務での実践的な活用方法、そして著作権に関する重要なポイントを、初任者にも分かりやすく解説します。
生成AIとは?基本をおさらい
生成AIとは、大量の情報を学習し、人間のような文章や画像を生成する技術のことです。代表的なツールにはChatGPTやGeminiがあります。これらのツールは非常に高性能ですが、その利用には慎重な姿勢が求められます。
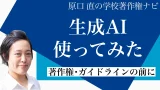
著作権の基本:知っておきたいルール
著作権は「知的財産権」の一つであり、音楽や文章、写真、イラストなど創作された瞬間に自動的に発生します。著作権のある作品は原則として作成者のものとされ、使用・複製・改変する場合には著作者の許可が必要です。
ただし、著作権法には例外規定もあります。学校では、著作権法第35条により授業の中で限定的に著作物を利用することが認められています。これは「学校内における教育目的の使用」に限られ、教員から児童生徒、またはその逆のやり取りに該当する範囲でのみ適用されます。
こうした基本を踏まえた上で、生成AIの活用にも著作権の視点が欠かせません。

最新動向:文科省ガイドラインと学校現場
2024年4月には文化庁の著作権課で生成AIと著作権についての議論が行われました。その後、7月に「初等中等教育段階における生成の利活用に関する検討会議」が設置され、教育関係者や専門家による検討が進められました。そして2024年12月には、文部科学省から正式なガイドラインが発表されました。
このガイドラインは文部科学省のウェブサイトに掲載されており、全文とともに概要版(1〜2枚程度)も用意されています。活用前には、最新情報と原文を必ず確認しましょう。

活用ポイント①:授業での利用
生成AIは、生徒の学びを支えるツールとして授業にも活用できます。
例えば英語のライティング授業では、生徒が書いた英文を入力することで、文法や表現に関するアドバイスを得ることができます。
利用上の注意点
- 使用目的を明確にし、学習指導の目標と一致しているか確認する
- 生徒の個人情報(氏名・生年月日など)を入力しない
- 出力結果は必ず教員がチェックし、生徒にそのまま使わせない
生成AIの出力は参考情報にとどめ、生徒が自ら考える力を育てる姿勢を大切にしましょう。
活用ポイント②:校務での利用
生成AIは授業以外にも、教員の業務(校務)を効率化する手段として有効です。
例えば、運動会のお知らせや感染症予防の案内など、保護者向けの通知文のたたき台作成に利用できます。生成された文案をもとに、学校の実情に応じて調整すれば、作成にかかる時間を大幅に短縮できます。
校務利用の注意点:
- 出力内容は必ず人間が確認・修正する
- 個人情報や機密情報は絶対に入力しない
活用ポイント③:著作権への配慮
生成AIの利用にあたって最も注意すべきことの一つが「著作権」です。知らず知らずのうちに、著作権を侵害してしまう可能性もあります。
注意すべき事例
- 有名なキャラクター名を入力し、似たイラストを生成する
- 歌詞の一部を使って詩を作らせる
こうした行為は著作権侵害にあたる可能性があります。また、以下の点にも留意しましょう:
- 特定の著作物を模倣するような指示は避ける
- 出力された内容が既存の著作物に似ていないか確認する
- 授業以外で使用する際は、著作権法第35条の範囲に注意する
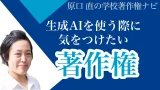
おわりに:安心して生成AIを活用するために
生成AIは、使い方を誤らなければ教育現場で大きな助けとなるツールです。授業や校務においては、その目的を明確にし、出力内容を丁寧にチェックしながら活用することが大切です。
そして、著作権に関する基本的な知識を持ち、常に慎重な対応を心がけましょう。
最初は戸惑うかもしれませんが、「こんな使い方ができるんだ」と実感できるようになれば、より創造的な活用アイデアも生まれてきます。生成AIを味方につけて、生成AIを学校で使ってみてください。
YouTube動画「【初任者向け】学校で生成AIを使う3つのコツ|授業・校務・著作権をやさしく解説」では、この記事の内容を詳しくお話しています。是非ご覧ください。