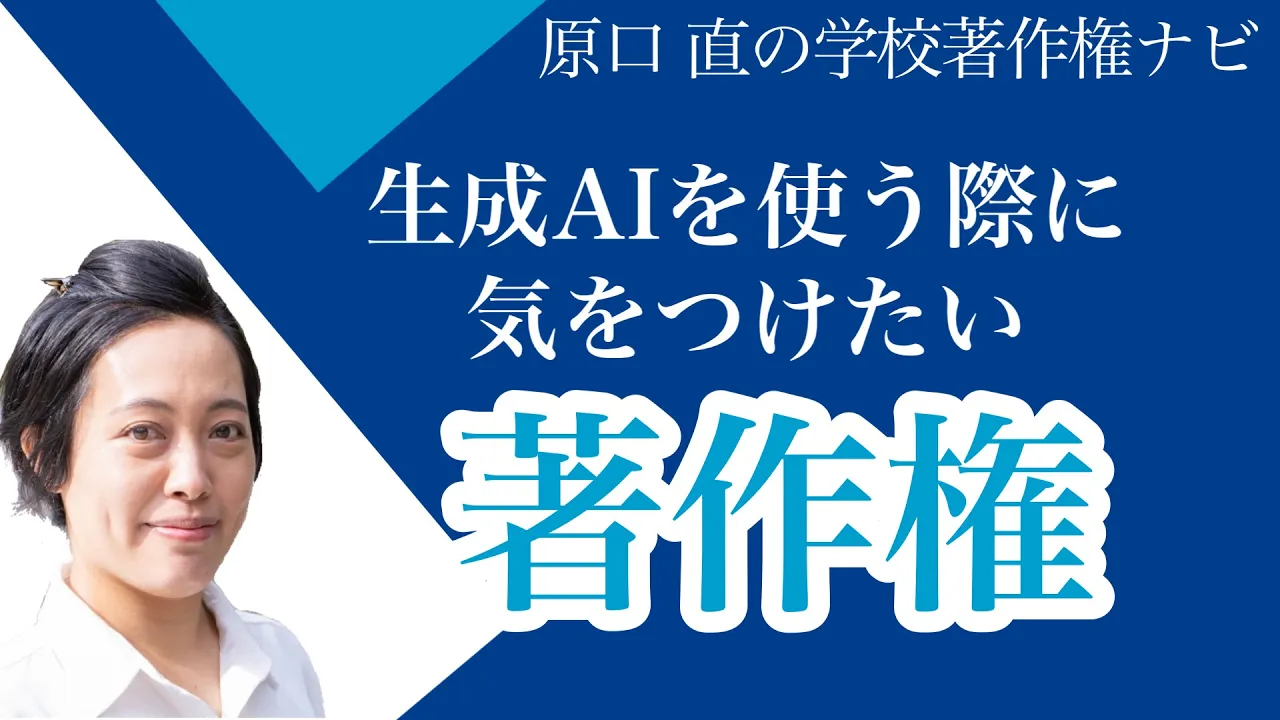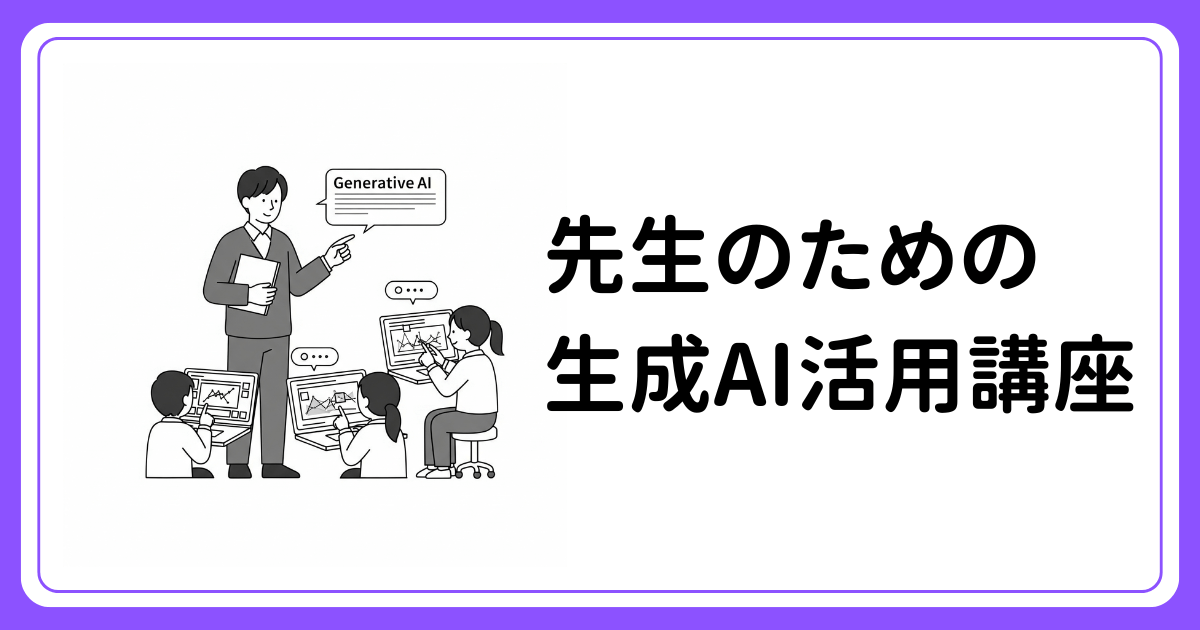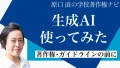近年、生成AI(Generative AI)の活用が急速に広がり、教育現場でもその利便性が注目されています。授業準備や校務の効率化に役立つ一方で、著作権に関する正しい知識を持たずに利用すると、思わぬトラブルを招く可能性もあります。
本記事では、学校で生成AIを安全かつ適切に使用するために押さえておきたい著作権の基本ポイントについて詳しく解説します。
生成AIと著作権の基本的な考え方
生成AIとは?
生成AIとは、過去の膨大なデータを学習して新しい文章、画像、音楽などを生成する技術です。
特に文章生成に優れており、学校だより、授業資料、テスト問題の作成など、さまざまな場面で活用が可能です。また、個別学習支援や校務の効率化にも役立つため、教育現場での活用が期待されています。
著作権とは?
著作権は、創作された作品を保護する法律です。
作品は作成者のものであり、使用する際には原則として著作権者の許可(許諾)が必要です。
ただし、著作権法第35条に基づき、学校の授業目的で使用する場合には一定の例外が認められています。この例外規定は、授業内の使用や教員と子供間のやりとりに限られており、授業外での利用には適用されない場合があります。

生成AI利用時の著作権に関する注意点
生成AIは便利なツールですが、その使用には著作権上の配慮が欠かせません。特に、入力する内容や生成された結果が他人の著作物とどのように関連するかを理解することが重要です。
ここでは、生成AIを使用する際に注意すべき具体的なポイントについて説明します。
入力時の注意
生成AIに指示を出す際(プロンプトの入力時)には、以下の点に注意が必要です。
- 有名なキャラクター名や商標を使用しない:商標権や著作権の侵害リスクを避けるために重要です。
- 指示と出力結果の過程を記録する:生成過程の透明性を確保し、著作権侵害のリスクを最小限に抑えるためです。また、トラブル発生時の証拠としても役立ちます。
出力結果の確認
生成AIが生成したコンテンツが他の著作物に類似していないかを確認することが重要です。
第35条は、授業の目的であれば著作物の利用が許可なしで可能な例外規定ですが、その範囲は授業内の使用や教員と子供間のやりとりに限られています。
授業外で使用する場合、たとえば保護者向けの資料や学校外イベントでの配布などはこの範囲外となり、著作権者の許諾が必要となる場合があります。こうした場合には、著作権の原則に則った対応が求められます。
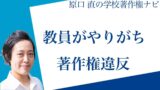
学校での具体的な活用例とガイドライン
文部科学省が示したガイドラインには、以下のような生成AI活用の具体例が紹介されています。
- テスト問題の下書き作成:生成AIが素早く草案を作成し、教師が確認・修正することで効率的な問題作成が可能です。
- 教材案の作成:授業準備の効率化に寄与し、多様な視点からの教材作成を支援します。
ただし、生成AIを使用する際は、常に著作権法(特に第35条)を意識し、授業の範囲内で著作物を適切に利用することが求められます。ガイドラインに沿った利用が、著作権侵害リスクを最小限に抑える鍵となります。
まとめ
生成AIは、教育現場での業務効率化に大きな可能性を秘めています。しかし、その利用には著作権法の理解と適切な対応が欠かせません。
文部科学省のガイドラインや関連資料(初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン)を参考に、安心して生成AIを活用していきましょう。そして著作権についても継続的に学んでいきましょう。
詳しくはYoutube動画「生成AIと著作権の注意点!学校現場での正しい使い方とは?」で解説しています。あわせてご覧ください。